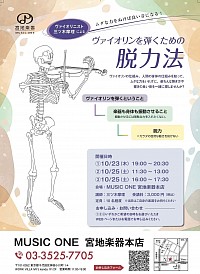赤いハリネズミの会・blog
《ヴァイオリンを弾くための”脱力法”》講座のお知らせ
10/23(火)、25(土)
宮地楽器《ヴァイオリンを弾くための”脱力法”》講座のお知らせ
***
ずっと私がやらせていただきたかった講座です。
私のこの20年の経験をまとめた、第1歩目です。
以下長文ですが、
「演奏と痛み」に興味があるかたは、よかったら~
********************************
今から20年近く前に、両肘を壊して、
両方の薬指と小指が曲がらなくなりました。
文字どおり、曲がらない。90度までいきませんでした。
(肘部菅症候群)
それまで、ヴァイオリンを弾くのは痛いものだと思っていました。
痛いことを我慢した結果がこれなのか?と驚愕しました。
それでも、専門の整形外科の先生、
仙人みたいな鍼治療の先生に、
本番に合わせて治療していただきながら、
なんとかお仕事をこなせました。
今、思い返すと、ぞっとしますが、
そのときは「ヴァイオリンが弾けなくなる」とは考えませんでした。
たぶん、無意識の防御線で、
普通はあそこで弾けなくなる方が多いのだとは思います。
「弾けるようにする」しか考えませんでした。
そこらへんが私はとてもラッキーでした。
治療の素晴らしい技術をもった先生方に出会えたこと、
家族や、友人たちの支えがあったから
「弾けなくなる」という考えに防御線を張れたのだと思います。
先生方の治療のおかげで、
指は曲がり、肘もあがるようになりました。
指は何もしていなくても、ずっと震えている状態でしたが、
とりあえず、動かしていないときに痛みが無くなったので
私は「この痛みとヴァイオリンに向き合わなきゃ」
と思いました。
このまま弾いても、同じことが起こるからと、
身体の勉強を始めました。
ヨガはその前からずっと続けていましたが、もっと専門的なこと、
アレクサンダー・テクニーク、ピラティス、
解剖学、フェルデンクライス。
どれも、マンツーマンで学びました。
それらを学びながら、
弦を押さえるのは、初心者がやる教本(セブシック)から
弓も持てなくなっていたので、弓の持ち方から、
研究しなおしました。
(だから生徒さんが弓が持てないお気持ち、
めちゃくちゃよくわかります)
ひとつずつの動きを、身体とヴァイオリンと音楽と、
相談しながらやり直しました。
コツコツそうやっていたら、
痛みが出ない弾き方をマスターするだけでなく、
肘を壊す以前にはできなかった技術的なことも、
できるようになりました。
私とヴァイオリンというものが、近くなった。より親密に。
そうすることで、なにより、音の響きが変わりました。
自分の心のドアを、ヴァイオリンが
ノックしてくれるようになりました。
それまでは、10時間練習もざらでしたが、
練習も、タイマーではかり痛みがでないように研究しました。
(練習っていうのは、
やりたいとき、やれるときに、
やりたいだけ、やれるだけやったら
絶対だめです。それは練習とはいいません。
今は「25分弾いて5分休む」を1セットのポモドーロ推奨。
1日トマト何個で練習を測ります。時間で測らない。
2時間ぶっつづけで弾くより、
2個トマトを並べるほうが効果的)
話をもどして、、、、、
これらのメソッドを根気強く、不器用な私に付き合って
レッスンしてくださった先生方のおかげで
今、私は演奏することができています。
メソッドというのは、
どれが正解、どれが効率良い、というわけでなく、
多角的に学びながら、
自分の中でまとめていかねばなりません。
自分の好きなカレーは自分でつくらないと。
演奏というものは、
とても個人的な、内面が関係してくることです。
だからこそ、人が奏でるということは、
上手い下手でなく、
人の心が響きあうことのできる「ツール」なのだと思います。
だからこそ、「楽器と自分」という関係性って
大切だと思っています。
音楽って身体から発せられるものだ。
********************************
これら身体の使い方を学んでいて、気が付いたのは、
「いかにヴァイオリンという楽器が、
身体本来の動きに添って造られているか」でした。
身体を活かす動きが、ヴァイオリンという楽器を活かし、
そこから音の響きは倍増するようなシステム。
それがヴァイオリンなんだなぁと。
小さいころからずっと一緒にいたのになぁ。
今まで気づきもしなかったなぁ。
人間の腕というのは、
鎖骨の微妙な傾き、
肩甲骨の肋骨をすべることで生まれる立体感
上腕骨の回転と回旋、
そして、前腕の二本ある骨の回旋と交差で動かします
それらで繊細な動きから、力強く動かす、
また、体に負担なく保持するなどが可能になります。
人間ならではの動きであり、二足歩行だからできることです。
基本的に、腕は、
「ものを支える動き」と「ものを押す動き」の
二種に分けて良いかなと思います
ヴァイオリンは弦から、
木である表板、裏板をいかに振動させるか、が要の楽器なので、
振動を止めてしまう「押す動作」は、ほぼ必要なく、
「いかに支えながら動かせるか」が重要であると思います。
その中で、「腕だけの重み」が、弦を押さえる左指に、
また、弦を摩擦して振動させる右手に
「いかに無駄な力みなく、重さだけを乗せるか」が重要になります。
それが、ヴァイオリンという独特の、
あの形、あの厚み、あの長さだから実現できること。
それがちょっと大きいだけで、小さいだけで、
流線形ではないだけで
腕の動きのバランス、腕と体のバランスが崩れてしまう。
(そのバランスが崩れては、楽器を振動させられなくなります)
体の仕組みと、ヴァイオリンという楽器を
結び合わせばあわせるほど、
すごく興味深いと思いました。
そんな楽器はほかには存在しないと思います。
だからこそ、16世紀からほぼ形がかわっていないのでしょう。
********************************
では、なぜ、ヴァイオリンはあの形になったのか?
実物が現存しないだけに、
絵画や彫刻から推察されることになってしまいますが、
数人の研究者の「夢あふれる成果」を知ることができました。
弓で弦を「こすり」始めたのはいつか?
(5000年前のラバナストロンという東洋の楽器の弓はほぼ今と近いかたち)
こすってみた振動に感動して、楽しんだのでしょうね。
弦をはじくより、長く振動できるじゃん!
人間の声が主流の音楽の世界に、
「人間の声よりも自由に歌える楽器が欲しかった」
それには、ひとつの楽器で、より幅広い音域をだしたい。
ユダヤ人の商人がクレモナに入ってきたことで、
ヴァイオリンは芸術の域へ。
居酒屋からメディチ家にまでつながる楽器となるわけです。
あなたが今、手にしているヴァイオリンも、
古代インドや東洋、ユダヤ人商人やメディチ家とつながっています。
********************************
もうひとつ、興味深いのが、
「身体を効率的に使う方向性は古代人のほうがよく知っていた」
という点です。
私が様々なメソッドを学ぶ中で、
いかに自分の身体を「思い込み」で
可動域や、柔軟性を狭めてきたかを知りました。
でも、昔のひとたちは、それらを当たり前に知っていた。
知っていたから、ヴァイオリンという楽器を生み出せたわけです。
さて、ここで講座のタイトル「脱力法」ってなんなのか?
タイトルにものすごく悩んで、
宮地楽器のヴァイオリンを作る男性と、
ヴァイオリンを弾く男性(私と同門)のおふたりが、
一緒に頭をひねって考えいてくださいました。
(こういうの、ひとりで考えてもできないので、助かりました)
小さいころから、
「無駄な力を抜いて」「力まないで」といわれながら
国内外、様々なヴァイオリニストにレッスンを受けてきた私。
しかし、抜いてると思っても力は抜けたなかったわけで、
ヴァイオリンを弾くのは痛いことになっていった。
そして肘を痛めて指が麻痺。
ヴァイオリンというのは、
『弦をこすって、“身体を共鳴させる”』楽器です。
それにはまず身体のつくり、ヴァイオリンのつくりを知ることが
ひとつの道になりました。
ヴァイオリンとは楽器と身体を振動させるものです。
それには、振動を止める動作をできるだけやめたい。
(それは身体も喜ぶし、音楽も喜ぶ)
振動を止めない「脱力」ってなぁに?
********************************
人間の脳みそには神経を新しくつなぐ可塑性が備わっています。
それはいくつになっても失われないもので、
何歳になっても、新しい動きを生み出せる。
思い込みの馬具を外して、ヴァイオリンを鳴らしてみませんか?
もちろん、悩んでいらっしゃることの解決にも、つながります。
10/23(木)19:00~20:30
10/25(土)11:30~13:00
10/25(土)16:00~17:30
どのクラスも10名様までで、ぼちぼち埋まってきています。
【お申し込み】
⇩講座お申し込みページ
https://www.miyajimusic.com/musicone/event/202510_vn_lesson/
ご予約は私のほうに直接ご連絡いただくのでも、お受けできます。
心の脱力にもつながってほしいなぁ。
ヴァイオリンを弾くことが、
より楽しくなっていただくきっかけになってほしい。
そういうコミュニケーションの時間を目指しています。
新鮮な驚きと、わくわく感ってなにより、
身体と音楽を健康にしますよね。
********************************
ここまでお読みくださった方、ありがとうございました。
良い一日を~